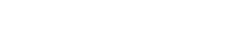目次
重機における税務上の耐用年数と減価償却、実際の使用寿命
工事現場で必要な重機には耐用年数があります。この耐用年数は、機械としての寿命のことではなく、税務上、減価償却資産としての寿命を意味しています。
ここでは、重機の耐用年数や、減価償却資産、実際の重機の寿命について紹介しましょう。
重機の耐用年数は減価償却ベースに考える
工事現場で必要な重機を購入する際に気になるのが、耐用年数です。重機は作業で酷使することもあり、耐用年数は使用頻度や作業環境が大きく影響します。そこで、重機の耐用年数は、減価償却ベースに考えることが一般的となっています。まずは、重機の耐用年数や減価償却について紹介しましょう。
耐用年数が示す言葉の意味
一般的に「耐用年数」といった場合、食べ物の消費期限のように「使用に耐える年数」を想像する方が多いことでしょう。ですが、重機において耐用年数という言葉を用いる場合は、税制上の「減価償却資産の耐用年数に関する省令」における「減価償却資産が利用に耐える年数」を表しており、重機が使えなくなるまでの年数ではありません。
そのため、耐用年数は現場においては気にするものではないということになります。
耐用年数と減価償却費の関係
会社の業務で使われる設備や機械など、使用した期間に応じてその価値が下がっていく資産のことを減価償却資産といいます。価値が下がると損をするように感じますが、機械は使用すれば使用するほど劣化していきますので、使用期間が長くなるほど価値はなくなるのは当然のことです。
もし、ある程度使用し老朽化した機械が新品と同じ価値と判断されてしまったら、会社としての保有資産が多いということになり、納税額は増えてしまいます。こういった税制上の不具合を改解消するため、減価償却資産の取得にかかった金額は、取得時に全額必要経費とせず、その資産の耐用年数にわたって分割し、必要経費としていくべきというのが減価償却費の考え方です。
減価償却費には毎年同額を計上する「定額法」と初年度に減価償却費を大きな金額で計上し、その後は毎年一定の償却率を掛けて、徐々に減少させていく「定率法」の2つがあります。
それぞれの計算式は以下のとおりです。
定額法:取得価額(購入額)×償却率(※)=減価償却費
定率法:未償却残高×償却率(※)=減価償却費
※購入した固定資産の法定耐用年数を基に設定。重機の種類により異なる。
例えば、耐用年数が8年の機械を800万円で取得した場合、8年間で合計800万円(均等に案分して1年で100万円)の減価償却費となります。
耐用年数は、「減価償却資産の耐用年数に関する省令」の「別表第2(機械及び装置の耐用年数表)」で決められています。2022年4月1日に施行された耐用年数では、「ブルドーザー、パワーショベルその他の自走式作業用機械設備」は8年と定められています。
なお、重機において、定率法での支払いを選択したい場合は、減価償却資産の償却方法の届出書や減価償却資産の償却方法の変更承認申請書を税務署に提出する必要があります。
中古で購入した重機の耐用年数
ブルドーザー、パワーショベル、その他の自走式作業用機械設備といった重機 を新車で購入した場合の耐用年数は8年ですが、中古の重機はすでに耐用年数の一部を経過しているため、通常の耐用年数を適用できません。その場合は「簡便法」を用いて、購入した中古重機の残りの耐用年数を算出します。
算出方法は、耐用年数から経過年数を引き、経過年数の20%に相当する年数を加え、1年未満の耐用年数は切り捨てます。例えば、耐用年数が8年で、経過年数が4年であれば、8-4+(4×0.2)=4.8年となり、0.8を切り捨て、税法上で適用される耐用年数は「4年」となります。
同様に、すべての耐用年数が経過した重機の場合は、8-8+(8×0.2)=1.6年となり、「1年」が耐用年数となります。ただし、耐用年数が2年未満の場合は、耐用年数を2年とするルールがありますので、結果的には「2年」が耐用年数となります。つまり、中古で購入した資産の耐用年数は、最低2年になるということです。
なお、中古重機の購入では少ないケースですが、購入金額が10万円未満の場合は即時償却として、損金経理ができることも覚えておきましょう。
重機の実際の使用可能年数は?
耐用年数が重機の寿命とは別のものだとすると、実際に稼働できる使用可能年数はどれくらいとなるのでしょうか。これは、重機の使用頻度や使い方が大きく影響するため、具体的に何年ということはできません。
一般的に、建設業で使うブルドーザーの寿命は、3,000~4,000時間の使用が目安といわれています。この使用時間は、「アワーメーター」と呼ばれる稼働時間を計測しているメーターでわかります。
とはいえ、4,000時間経過したら必ず壊れるわけではなく、定期的なメンテナンスなどによって寿命は延びていきます。油圧システムの清掃のほか、燃料タンクやウォーターセパレーターの水抜きといった日々のメンテナンスは、ブルドーザーの寿命延長につながりますので、こまめに行うようにしましょう。
重機のレンタルならJukiesにお任せください
重機を購入する場合は減価償却資産として、手間のかかる税務処理をしなければいけません。そのため、使用頻度の低い重機は、購入するよりもレンタルをしたほうが効率的です。Jukies(ジューキーズ)では、さまざまなタイプの重機をご用意しています。重機をレンタルする際は、Jukiesをご検討ください。